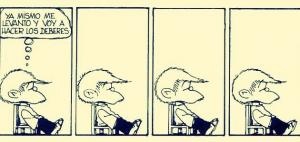自己決定理論:それが何であり、それが提案するもの
人間は定義上、活動的な存在です。私たちは、生き続けるために多種多様な行動を継続的に行っています。 環境に適応するか、私たちのサイクルを通して生じる変動とニーズに対処できるように発達する 重要。 私たちは、行動するために、内部的にも環境で利用可能なレベルでも、自由に使える手段を使用します。
しかし... なぜ私たちは行動するのですか? 何が私たちを動かしますか? これらの一見単純な質問は、何が私たちを行動に駆り立てるのかについて、非常に多様な理論の精緻化につながりました. この点に関して一連のサブセオリーを実際にまとめているこれらのセオリーの 1 つは、 自己決定論. この記事全体で説明するのは後者についてです。
- 関連記事:「心理学における二元論"
自己決定理論: それは何を教えてくれるのか?
それは自己決定理論の名前を、主に Decí と Ryan は、人間の行動がどの程度影響を受けているかを立証することを目指しています。 違う 行動への動機に影響を与える要因、自己決定のアイデア、または基本的な説明要素として何をどのように行うかを自発的に決定する能力に特に重点を置いています。
自己決定理論の主な目的は、人間の行動を理解することです。 すべての文化の人間が遭遇する可能性のあるすべての状況に一般化され、あらゆる領域、領域、または領域に影響を与えることができます。 重要なドメイン。
この意味で、 この理論は、分析する主な要素としてモチベーションに焦点を当てています、さまざまな人間のニーズによって生成されたエネルギーの蓄積の存在を評価し、後でそのニーズの満足に向けた方向性または方向性を獲得します。
この意味で、それらは非常に重要であることを考慮に入れなければなりません 当該人物の性格および生物学的および自伝的要素、彼らの行動が動く文脈とそれが実行される特定の状況、 互いに影響し合い、さまざまなタイプの外観に影響を与える要素 モチベーション。
自己決定とは、ますます内的な力を通じて、私たち自身が自発的に私たちの行動を指示する度合いです。 行動を実行することを必要とする環境要素によって仲介されるのではなく、行動を実行したいという意志と欲求のますます特徴的な特徴 アクション。 私たちは発達する傾向がある活動的な存在です、与えられた外部要素と内部要素の両方のレベルで、知覚された経験を成長させ、求め、統合します。 これらすべてにより、現在および将来、私たちを満たすためのリソースを確保できるようになります ニーズ。 したがって、環境から来るものと生得的で衝動的なものの両方が重要です。
私たちは、さまざまな心理的パラダイムの概念を統合し、そこから出発する理論に直面しています。その中で、行動的および人道的なパラダイムが際立っています。 一方では、そのメカニズムを説明する情報を厳密かつ科学的に検索しています。 私たちは自分の行動を動機付けの目標の達成に向けます(行動主義者と同様の方法で)。 活動的な存在としての人間のビジョンを獲得し、目的と目標に向けられること 人間性心理学の特徴。
同様に、この理論はほぼすべての分野に適用可能であることを考慮に入れる必要があります。 あらゆる種類の活動の実施: 学問的なトレーニングや仕事から余暇まで、人間関係を通じて 対人。
- あなたは興味があるかもしれません: "モチベーションの種類: 8 つのモチベーションの源"
5つの偉大なサブセオリー
前述したように、自己決定理論はマクロ理論として識別できます。 自分自身の決定に関する動機付けの機能を調査することを目的としています 行動。 これは、動機と自己決定の問題に取り組むために、理論自体が相互に関連する一連のサブ理論で構成されていることを意味します。 これらのサブセオリーは、主に次の 5 つです。
1. 基本的な心理的ニーズの理論
自己決定の理論を構成する主要な理論の 1 つは、基本的な心理的ニーズの理論です。 これらのニーズは、人間がやる気を感じるために必要な精神構造を指します。 単に生理学的な要素(食べる必要性や 飲む)。 このアプローチ内で実施されたさまざまな研究により、 人間の行動を説明する少なくとも 3 種類の基本的な心理的欲求: 自律性の必要性、自己能力の必要性、絆または関係の必要性。
これらの最初のものである自律性は、人間 (および他の存在) が知る必要性を指します。 または、自分自身の行動を通じて、自分自身の生活や日常生活に影響を与えることができる存在であると考えています。 現実。 この必要性は、対象者が自分の行動を現実的で明白な効果を持つものと見なし、自分の行動を行使することができることを意味します。 自分が何をするか、何を伴うかをある程度コントロールできます。 選ぶ。 それは個人のアイデンティティの出現の基本です、そしてそれが完全に発達していない場合、受動性と依存性の行動、そして無用感と絶望感が現れるかもしれません.
自分の能力を認識したいという欲求は、基本的に前の能力と関連しています。 それは彼ら自身の行動に基づいて起こりますが、この場合、私たちが実行するのに十分なリソースを持っているという信念に焦点を当てています. 行為。 それは、私たちには能力があるという信念であり、熟練しているという感覚です。、私たちが自律的に実行することを選択したアクションは、私たちの能力のおかげで実行でき、何が起こるかに一定の影響を与えることができます.
最後に、関係やつながりの必要性は、人間のような群生する生き物では常にあります。 私たちはグループの一員であると感じる必要があり、ポジティブな方法で相互作用し、 相互支援。
2. 因果方向の理論
自己決定の理論のもう一つの基本的な要素は、自己決定の理論のそれです。 何が私たちを動かすか、または私たちが向かっている方向を解明することを意図した因果的方向性 私たちの努力。 この意味で、この理論は、内発的または自律的、外因的または制御的、非個人的または無動機という 3 つの主なタイプの動機の存在を確立します。
内発的または自律的な動機付けの場合、これはパフォーマンスが向上するような方法で私たちを動機付ける力を表します。 内力から来る、それを行う喜びのために行動を実行します。 前述のすべての基本的なニーズが十分に満たされる時期の一部であり、自分の意志と選択のみに基づいて行動する時期です。 これは、より高度な自己決定を意味し、精神的健康との関連性が高いタイプの動機です。
対照的に、外発的動機付けは、いくつかの満足の欠如から生じます。 を実行することによって満たされることを意図した心理的または生理学的ニーズ 行為。 私たちは、欠乏状態の軽減を可能にする、または促進するために実行される行動に直面しています。 一般的 行動は、ニーズを満たすために制御されていると見なされます. ある程度の自己決定はありますが、これは内発的動機付けよりも少ない程度です。
最後に、非個人的な動機ややる気の低下は、能力と自律性の欠如の感覚に由来するものです。 私たちの行動は起こりうる変化を予測せず、現実に影響を与えず、私たちや自分に何が起こるかを制御できない 現実。 すべてのニーズが満たされず、絶望とやる気の欠如につながります。
3. 認知的評価理論
自己決定の理論を構成するサブセオリーの 3 番目は、この場合、生来の利益と自己の利益の存在 環境(外部または内部)で発生するイベントを受け取り、認知レベルで異なる評価を行い、さまざまな程度の評価を生成します。 モチベーション。
被験者の重要な経験は、環境に対する彼らの行動の結果と影響に関する学習履歴と同様に、これに参加します。 これらの興味は、内発的動機付けのレベルの違いを説明するために分析されます、しかし、それが外因性にどのように影響するか、またはどのような側面や現象がモチベーションの低下を助長するかについても評価します. この関心は、世界との相互作用が基本的なニーズの達成をどのように許可するか、または許可しないかについての認識からも導き出されます。
結論として、認知評価の理論は、現実のさまざまな側面に対する私たちの関心を予測する主な要素は、 それらは、私たちが行うコントロールの感覚と帰属、認識された能力、動機の方向性(何かを達成することであるかどうか)、および状況または外的要因です。
4. 有機的統合理論
有機的統合の理論は、さまざまな種類の外的動機付けの程度と方法を分析しようとする提案であり、 自分自身の行動の規制の内面化または同化の程度に応じて.
この内在化は、要素への依存をやめる動機付けの能力を徐々に生み出します。 外的動機と内発的動機が生まれ、価値観と規範の獲得に基づく自己の発達を通じて出現します。 社交。 この意味で、外発的動機付けは、どのような行動規制が行われるかによって、大きく4つのタイプに分けることができます。
初めに 外部規制があります報酬を得るため、または損害や罰を回避するために行動し、その行動は外部によって完全に指示および制御されます。
やや内面化された規制では、行動が実行され続けているにもかかわらず、導入された規制による外因性動機が発生します。 報酬を獲得したり、罰を回避したりするために実行される場合、これらの管理または回避は、エージェントが実行する内容に依存するのではなく、内部レベルで発生します 外部の。
その後、識別された規制による外因性動機を見つけることができます、彼らは実行された活動に自分の価値を与え始めます(報酬/罰を求め/回避することによって実行され続けているという事実にもかかわらず).
4番目と最後の、同じ名前の動機の本質的な規制に非常に近いですが、 それにもかかわらず、それは外的要因によって支配され続けており、規制によって生じる外的動機です。 統合されています。 この場合、行動はそれ自体がその人にとって肯定的でお世辞だと見なされ、報酬や罰を評価することはありませんが、それ自体が楽しみを生み出すため、まだ実行されていません.
5. 目標内容理論
最後に、さまざまな著者がそれを自己決定の理論に組み込んでいませんが、それに影響を与える最も関連性の高い理論のもう1つは、目標内容理論です. この意味で、モチベーションの場合と同様に、内的および外的目標があります。 これらの最初のものはに基づいています 心理的幸福と自己啓発の探求、主に個人の成長、所属、健康、コミュニティへの貢献、または生成性の目標で構成されています。
外因性に関しては、それらは独自の目標であり、人の外部から何かを取得して存在することを目的としています 環境に依存する: 私たちは主に外見の必要性、経済的/経済的成功、そして 名声/社会的配慮。 ただし、目標が内的または外的であるという事実は、私たちをそれに導く動機が次のとおりであることを意味しません。 必然的にその形容詞を共有するもの:外的目標を達成するための内的動機を持つことが可能です。 逆に。
参考文献:
- ライアン、R.M. & Deci, E.L. (2000)。 自己決定理論と内発的動機付けの促進、社会的発展と幸福。 アメリカの心理学者、55 (1): 68-78。
- Stover, J.B., Bruno, F.E., Uriel, F.E. およびLiporace,M.F. (2017)。 自己決定理論: 理論的レビュー。 心理学の展望、14(2)。